 こんにちは、Antumです。 見に来ていただきありがとうございます!今日は、「食べすぎることの心理的な背景って何?」について、考察してみたいと思います。
こんにちは、Antumです。 見に来ていただきありがとうございます!今日は、「食べすぎることの心理的な背景って何?」について、考察してみたいと思います。
食べすぎの心理的背景
1. 不安から食べる
「なんの不安?」と思うかもしれませんね。私の場合は、
「食べられるうちに食べておかないと、後でお腹が空いちゃうかもしれない…」
という不安です(笑)。
飽食の時代に「食いっぱぐれる」ことなんてないのに、なぜ不安を感じるのか。掘り下げてみると、幼少期の記憶が関係していました。
私は3人兄弟で、下に2人の弟と妹がいます。そのうち一人がとても食いしん坊で、よく食べる子でした。家族が買ってきたミスドも、早めに食べないと欲しいドーナツがなくなるどころか、そもそもドーナツ自体が残っていない!…なんてこともよくありました。
そんな経験から、「今すぐ食べないと不安」という感覚が自分の中に育ったのかもしれません。
最近では、「今食べなくても後で食べられる。私のものは誰も取らない。」と思える瞬間が増えてきて、少しずつ不安から解放されつつあります。
2. ストレス解消に食べる
これは多くの方が経験しているのではないでしょうか。私もよくやります(笑)。
食べることって幸せですよね。美味しいものが多い日本に生まれてよかったと思います。ただし、ストレス解消のために食べすぎると、楽しさが嫌悪感に変わってしまうこともあります。
実際、ある食べ物にはセロトニン・ドーパミン・オキシトシンといった「幸せホルモン」を分泌させる作用があり、人間の本能として抗えない部分もあるのです。
ただ、本能のままに食べ続けると心身が苦しくなることも。そんなときはストレスの根本を見直すことが大切なのかもしれません。
3. 仮の空腹(偽の食欲)
実はエネルギーは足りているのに、脳が「お腹が空いた!」というサインを出してしまうことがあります。これを仮の空腹と呼びます。
要因のひとつは血糖値の急上昇と急降下。これを防ぐために、以下の工夫が役立ちます。
- 水やお茶を飲んで「喉の渇き」と「空腹」を区別する
- よく噛んで食べる
- ガムを噛む、食後に歯磨きをする
- 軽い運動を取り入れる
- 十分な睡眠をとる
- ヘルシーなおやつを準備しておく
- 食事は「野菜から食べる」など食べ方を工夫する
つまり、体に必要なエネルギーを適切に取り入れることが大切だということですね。
まとめ
食べすぎの背景には、不安・ストレス・仮の空腹など、心や体の仕組みが大きく関わっています。
ご自身の「食べすぎパターン」に思い当たることはありましたか?もしあれば、ぜひコメントやメッセージで教えてください!



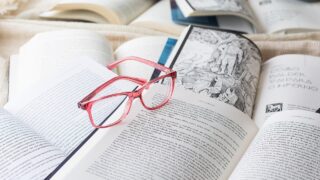
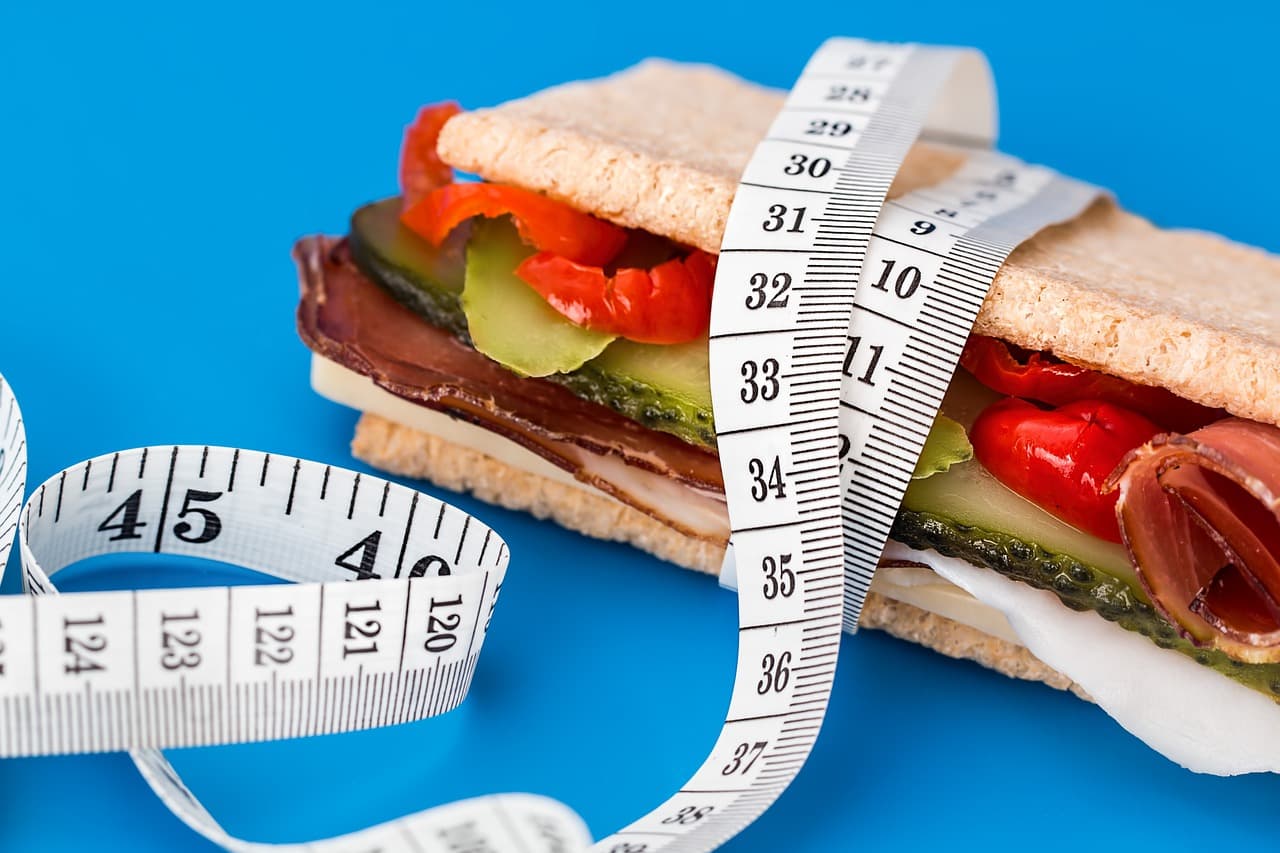


コメント